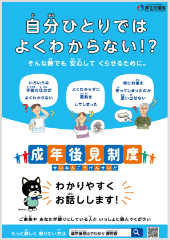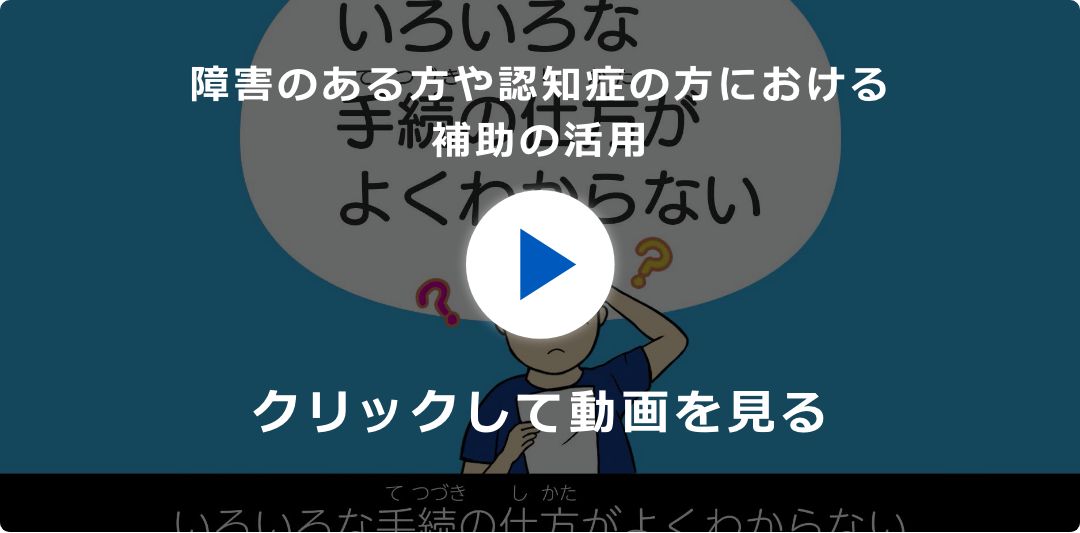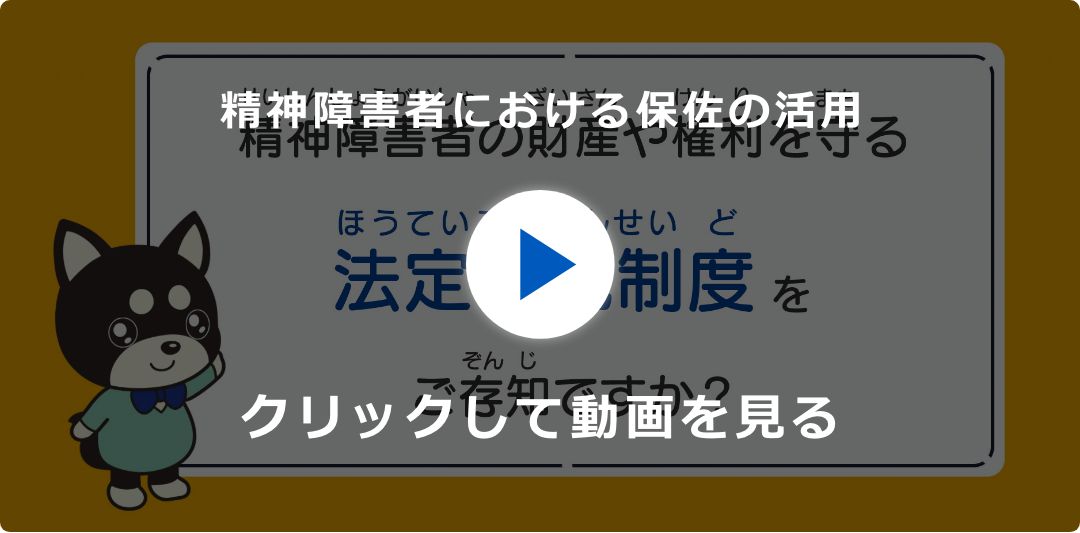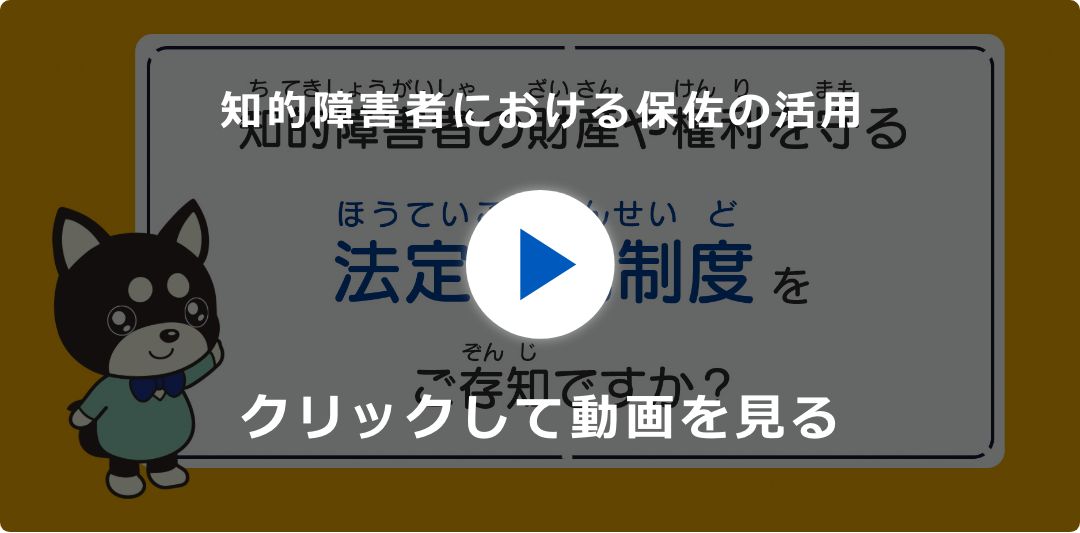ご本人・家族・地域のみなさまへ法定後見制度とは(手続の流れ、費用)
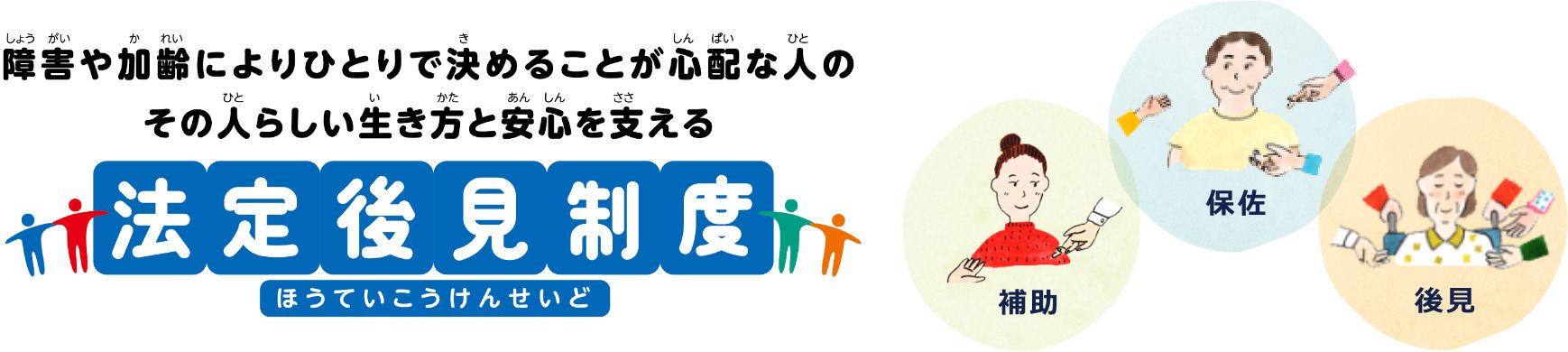

ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
法定後見制度の3つの種類(類型)
法定後見制度は、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。
後見

対象となる方
多くの手続・契約などを、
ひとりで決めることがむずかしい方
法定後見制度の詳細
| 対象となる方 | 重要な手続・契約の中で、 ひとりで決めることに心配がある方 |
|---|---|
| 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為※1 | 申立てにより裁判所が定める行為※2 |
| 成年後見人等が代理することができる行為※3 | 申立てにより裁判所が定める行為 |

不安になったご本人が長男に相談し、長男が家庭裁判所に補助開始の申立てをし、併せて他人からお金を借りたり、他人の借金の保証人となることについて同意権付与の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て、ご本人について補助が開始され、長男が補助人に選任されて同意権が与えられました。その結果、ご本人が長男に相談せずに、貸金業者から借金をしたような場合には、長男がその契約を取り消すことができるようになりました。
| 対象となる方 | 重要な手続・契約などを、 ひとりで決めることが心配な方 |
|---|---|
| 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為※1 | 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 |
| 成年後見人等が代理することができる行為※3 | 申立てにより裁判所が定める行為 |

症状
ご本人は、持ち家の老朽化が心配になり、売却して安心したいとの希望を持つようになりましたが、ご自身で進めることは困難でした。そのため、長男にお願いしたいと思い、保佐開始と併せて、持ち家の売却に関する代理権付与も申立てました。家庭裁判所の審理を経て、ご自身について保佐が開始され、長男が保佐人に選任されました。
長男は、家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け、ご自身の自宅を売却する手続を進めました。
| 対象となる方 | 多くの手続・契約などを、 ひとりで決めることがむずかしい方 |
|---|---|
| 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為※1 | 原則としてすべての法律行為 |
| 成年後見人等が代理することができる行為※3 | 原則としてすべての法律行為 |

家庭裁判所の審理を経て、ご本人について後見が開始されました。そして、親族が遠方&高齢で後見人に就任することが困難であり、相続登記など専門知識を要する後見事務が想定されるため専門職の選任が適切と裁判所が判断し、司法書士が選任されました。併せて専門職団体が設立した公益社団法人が成年後見監督人に選任されました。
※1 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
※2 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
※3 ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
※ 補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。
補助の活用
保佐の活用
精神障害者 における保佐の活用
法定後見制度の中の「保佐」について、制度を利用されている精神障害者の方の生活やインタビューから、保佐人の活動や制度利用の流れ、制度のメリットや注意点についてご紹介します。権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関や、法人後見が登場します。
法定後見開始の審判の申立てに必要な費用について
| 補助 | 保佐 | 後見 | |
| 申立 手数料 (収入印紙) |
800円※1 | 800円※2 | 800円 |
| 登記 手数料 (収入印紙) |
2,600円 | 2,600円 | 2,600円 |
| その他 | 連絡用の郵便切手※3、鑑定料※4 | ||
- 補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。
- 保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になります。
- 申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。
- 後見と保佐では、必要なときには、ご本人の不安の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、10万円以下となっています。
- 申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。(申立てに必要な書類については、申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。)
- 経済力に余裕がない方については、日本司法支援センター(通称「法テラス」)が行う民事法律扶助による援助(申立代理人費用の立替えなど)を受けることができる場合があります。
詳しくは法テラスの窓口TEL 0570-078374 (おなやみなし)へお電話ください。
また、法定後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市町村もあります。詳しくは各市町村の窓口へお問い合わせください。

成年後見制度の利用を検討している方は、
お近くの権利擁護支援相談窓口へ
ご相談ください。

 ホーム
ホーム